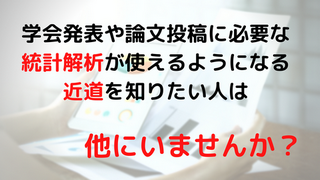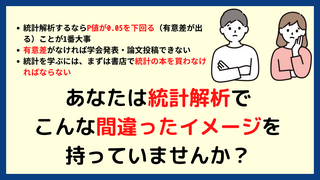いままでの方法と比べて、格段にいいとか、際立っていいとか、じゃなくてもいい場合がある。
ダメじゃなければいい。
劣っていなければいい。
劣っていなければいいという検定方法が、非劣性(ひれっせい)検定だ。
じゃ、どういうときが劣っていないって言うのか?
- 非劣性マージンとは?劣っているとは?劣っていないとは?
- 非劣性マージンの決め方
- 非劣性マージンの決め方例
- 非劣性検定 割合の場合
- 非劣性検定 割合の検定を最尤推定量で行うには?
- 非劣性検定 割合の場合 エクセル計算機
- 非劣性検定 平均値の場合
- 非劣性検定 平均値の場合 エクセル計算機
- まとめ
- 参考書籍
非劣性マージンとは?劣っているとは?劣っていないとは?
劣っていないとはどういう状態を言うのか?
劣っているとはどう状態なのか?
あなたは聞いて回ったことがあるだろうか?
臨床医は知っていると思うだろうか?
実は誰もわからないのだ。
非劣性検定で一番の問題はこの点だ。
「これ」以上劣っていたら、劣っているとする、という閾値(しきいち)を決める。
「これ」が非劣性マージンと呼ばれる幅だ。
だが、非劣性マージンは何が正解か誰もわからない。
非劣性マージンの決め方
参考になるスライドセットを見つけた。
非劣性マージンを決めるときに必要なのは、標準治療とプラセボの効果の差と、保持率とか維持率と呼ばれる数値。
標準治療の効果と保持率=維持率の掛け算で、非劣性マージンを決める。
では、保持率=維持率とは何か?
標準治療のプラセボに対する効果の何割は効果があるか?ということ。
どんなに効果がなくても、標準治療の効果の半分は効果がある。
もしくは効果があってほしい、など。
新しい治療はまだ効果がよくわからないから、最悪でも標準治療の効果のどのくらいは効果がある、ということは実はわからない。
だから、保持率=維持率は、あいまいだ。
主観なのだ。
もしくは願望。
どこまでいっても議論が尽きない理由がわかる。
非劣性試験の最大の弱点だ。
現実は、たくさん試験が行われていて、何らかの理屈をつけて適切な試験とみなされている。
その結果、効果は変わらないが、副作用が少ない治療法が生まれている。
どこまでも怪しさが残るが、全否定するほどでもない。
これが非劣性マージン、非劣性検定、非劣性試験だ。
非劣性マージンの決め方例
例 1:プラセボとの差の半分

出典:
非劣性検定 割合の場合
Rのスクリプトを以下に示す。
non.inferior <- function(nA, nB, rA, rB, DELTA, conf.level=0.9){ METHOD <- "Non-Inferiority Test (Dunnett-Gent)" pB.star <- (rA+rB+nA*DELTA)/(nA+nB) se.delta.hat <- sqrt(((pB.star-DELTA)* (1-pB.star+DELTA))/nA+(pB.star*(1-pB.star))/nB) pA.hat <- rA/nA pB.hat <- rB/nB STATISTIC <- (pA.hat-(pB.hat-DELTA))/se.delta.hat names(STATISTIC) <- "Z" PVAL <- 1-pnorm(STATISTIC) se <- sqrt(pA.hat*(1-pA.hat)/nA+pB.hat*(1-pB.hat)/nB) delta <- pA.hat-pB.hat WIDTH <- qnorm(1-(1-conf.level)/2) CINT <- c(delta - WIDTH*se, delta + WIDTH*se) attr(CINT, "conf.level") <- conf.level RVAL <- list(statistic=STATISTIC, p.value=as.numeric(PVAL), estimate=c(pA=pA.hat, pB=pB.hat, pBstar=pB.star), conf.int=CINT, method=METHOD) class(RVAL) <- "htest" return(RVAL) } non.inferior(nA=128, nB=127, rA=64+37, rB=57+39, DELTA=0.1)
Rコンソールにコピペすれば使える。
臨床的に意味のある最小の差(DELTA)が非劣性マージンだ。
どんなに最悪でもそこは下回らないという限界点。
- pA.hat: 試験薬の有効率
- pB.hat: 標準薬の有効率
DELTA: 臨床的に意味のある最小の差→10%(0.1)とする
- rA: 試験薬群の有効症例数→64人と37人とする
- nA: 試験薬群のサンプルサイズ→128とする
- rB: 標準薬群の有効症例数→57人と39人とする
- nB: 標準薬群のサンプルサイズ→127とする
STATISTICSが検定統計量で、漸近的に正規近似できる検定統計量だ。
non.inferiorが自作関数名だ。
non.inferior()で使う。
結果は以下の通り。
> non.inferior(nA=128, nB=127, rA=64+37, rB=57+39, DELTA=0.1) Non-Inferiority Test (Dunnett-Gent) data: Z = 2.5561, p-value = 0.005293 90 percent confidence interval: -0.05314985 0.11946383 sample estimates: pA pB pBstar 0.7890625 0.7559055 0.8227451
p値は片側で出している。
非劣性は最低この点は下回らないという仮説で、片側しか興味がないため、興味がある側の片側p値を出す。
90%信頼区間を出力しているのも、下限5%のラインを見るためだ。
非劣性マージンー10%(-0.1)よりも、信頼区間の下限が大きく-0.05のため、非劣性と言えるわけだ。
ただし、有効性100%の場合は計算できない。
> non.inferior(nA=188, nB=91, rA=188, rB=91, DELTA=0.1) Non-Inferiority Test (Dunnett-Gent) data: Z = NaN, p-value = NA 90 percent confidence interval: 0 0 sample estimates: pA pB pBstar 1.000000 1.000000 1.067384 Warning message: In sqrt(((pB.star - DELTA) * (1 - pB.star + DELTA))/nA + (pB.star * : NaNs produced
非劣性検定 割合の検定を最尤推定量で行うには?
正規近似は100%を超えてしまうときは使えない。
現実には、両群とも有効率100%がありうる。
有効率100%を非劣性検定するには、最尤推定量に基づく検定を利用する必要がある。
pB.star: 帰無仮説(H0:pA=pB-DELTA)の下でのpB
の計算が前節の正規近似と異なり、ややこしい。
non.inferior.likelihood <- function(nA, nB, rA, rB, DELTA, conf.level=0.9){ METHOD <- "Non-Inferiority Test (Likelihood Method)" pA.hat <- rA/nA pB.hat <- rB/nB a <- nA+nB b <- -1*(nB+nA+rB+rA+DELTA*(nA+2*nB)) c <- nB*DELTA^2+DELTA*(2*rB+nA+nB)+rB+rA d <- -rB*DELTA*(1+DELTA) v <- b^3/(27*a^3)-(b*c)/(6*a^2)+d/(2*a) u <- sign(v)*sqrt(b^2/(9*a^2)-c/(3*a)) w <- (pi+acos(v/u^3))/3 pB.star <- 2*u*cos(w)-b/(3*a) se.delta.hat <- sqrt(((pB.star-DELTA)* (1-pB.star+DELTA))/nA+(pB.star*(1-pB.star))/nB) STATISTIC <- (pA.hat-(pB.hat-DELTA))/se.delta.hat names(STATISTIC) <- "Z" PVAL <- 1-pnorm(STATISTIC) se <- sqrt(pA.hat*(1-pA.hat)/nA+pB.hat*(1-pB.hat)/nB) delta <- pA.hat-pB.hat WIDTH <- qnorm(1-(1-conf.level)/2) CINT <- c(delta - WIDTH*se, delta + WIDTH*se) attr(CINT, "conf.level") <- conf.level RVAL <- list(statistic=STATISTIC, p.value=as.numeric(PVAL), estimate=c(pA=pA.hat, pB=pB.hat, pBstar=pB.star), conf.int=CINT, method=METHOD) class(RVAL) <- "htest" return(RVAL) } non.inferior.likelihood(nA=128, nB=127, rA=64+37, rB=57+39, DELTA=0.1)
結果は以下の通り。
p値がほんの少し大きくなり、帰無仮説の下でのpB(pBstar)は、ほんの少し小さく見積もられている。
> non.inferior.likelihood(nA=128, nB=127, rA=64+37, rB=57+39, DELTA=0.1) Non-Inferiority Test (Likelihood Method) data: Z = 2.5181, p-value = 0.0059 90 percent confidence interval: -0.05314985 0.11946383 sample estimates: pA pB pBstar 0.7890625 0.7559055 0.8129256
最尤推定量に基づく方法なら有効性100%でも検定できる。
> non.inferior.likelihood(nA=188, nB=91, rA=188, rB=91, DELTA=0.1) Non-Inferiority Test (Likelihood Method) data: Z = 4.5704, p-value = 2.434e-06 90 percent confidence interval: 0 0 sample estimates: pA pB pBstar 1 1 1
最尤推定量に基づく方法で検定しておけば、いつでも問題ない。
R の TOSTER パッケージを使った方法(twoprop_test 関数)
R の TOSTER パッケージを使うと、以下のように簡単に計算できる
library(TOSTER) twoprop_test(p1=(64+37)/128, p2=(57+39)/127, n1=128, n2=127, null=-0.1, alternative="greater")
結果は、以下のように出力される

p1 のほうが大きい(greater)という対立仮説で、帰無仮説(null)には、0 の代わりに、-0.1 とする
これによって、-0.1 が棄却されれば、少なくとも ‐0.1 よりも小さいことはないと言えることになり、非劣性マージン ‐0.1 よりは大きいことが示されたことになる
P 値は、上記のスクリプトによる結果と同様の、0.005579 となり、差の 90 % 信頼区間の下限を見ると、-0.1 よりも大きい、約 ‐0.053 となっていて、結果が整合していることがわかる
非劣性検定 割合の場合 エクセル計算機
母比率の非劣性検定(最尤推定量に基づく方法)を計算するエクセル計算機を作ったので、よければどうぞ。
割合の非劣性検定 計算機【エクセル計算機】 | TKER SHOP
使い方解説動画も、よければどうぞ。
非劣性検定 平均値の場合
変化量の平均値のような場合、非劣性検定はどうやるか?
帰無仮説と対立仮説
は以下の通りだ。
臨床上意味のある最小の差を引いて、同じかそれよりも劣る、が帰無仮説。
対立仮説は臨床上意味のある最小の差を引くと、少なくともそのレベルは上回る効果がある。
non.inferiority.mean <- function( nA, xbarA, sdA, nB, xbarB, sdB, Delta, conf.level=.9){ data.name <- sprintf("\nN_A = %s, Mean_A = %s, SD_A = %s\n N_B = %s, Mean_B = %s, SD_B = %s\nDelta = %s", nA, xbarA, sdA, nB, xbarB, sdB, Delta) METHOD <- "Non-inferiority test (Mean)" df <- nA-1+nB-1 names(df) <- "df" SE <- sqrt((1/nA+1/nB)*(((nA-1)*sdA^2+(nB-1)*sdB^2)/df)) STATISTIC <- (xbarA - (xbarB - Delta))/SE names(STATISTIC) <- "T" PVAL <- 1 - pt(STATISTIC, df) delta <- xbarA - xbarB WIDTH <- qt(1-(1-conf.level)/2, df) CINT <- c(delta-WIDTH*SE, delta+WIDTH*SE) attr(CINT, "conf.level") <- conf.level RVAL <- structure(list(statistics=STATISTIC, parameter=df, p.value=as.numeric(PVAL), data.name=data.name, conf.int=CINT, method=METHOD)) class(RVAL) <- "htest" return(RVAL) } non.inferiority.mean(nA=46, xbarA=34.5, sdA=32.02, nB=44, xbarB=29.7, sdB=28.42, Delta=7)
結果は以下の通り。
平均の差は4.8で、これはどんなに悪くても-7よりは小さくはならないはず、というのが証明したい仮説だ。
計算結果、片側p値は0.034で、有意水準片側5%とすると統計学的有意。
90%信頼区間(片側5%)の下限は-5.8で、-7より大きいため、最悪でも-7よりは悪くない。
よって、非劣性が証明された。
> non.inferiority.mean(nA=46, xbarA=34.5, sdA=32.02, nB=44, xbarB=29.7, sdB=28.42, Delta=7) Non-inferiority test (Mean) data: N_A = 46, Mean_A = 34.5, SD_A = 32.02 N_B = 44, Mean_B = 29.7, SD_B = 28.42 Delta = 7 T = 1.8459, df = 88, p-value = 0.03413 90 percent confidence interval: -5.826446 15.426446
R の TOSTER パッケージを使った方法(tsum_TOST 関数)
R の TOSTER パッケージの tsum_TOST を使うと、同じ計算が簡単にできる
install.packages("TOSTER") # インストールは 1 回だけ実行 library(TOSTER) tsum_TOST(m1=34.5, sd1=32.02, n1=46, m2=29.7, sd2=28.42, n2=44, eqb=-7)
結果は以下のように表示される

TOST Lower の p.value が片側 p 値である
Effect Sizes の Raw 行の C.I. 下限値が 片側 5 % の下限値である
ともに、上記の計算と一致している(下限値は少しずれている。計算式違いのためと思われる)
非劣性検定 平均値の場合 エクセル計算機
平均値の非劣性検定を計算するエクセル計算機を作ったので、よければどうぞ。
平均値の非劣性検定 計算機【エクセル計算機】 | TKER SHOP
使い方解説動画も、よければどうぞ。
まとめ
非劣性検定を割合の場合と平均値の場合に分けて紹介した。
割合の場合は最尤推定量の基づく方法がベターだ。
非劣性検定は、非劣性マージンの設定が問題となる。
非劣性マージンが適切に設定され、サンプルサイズが適切に見積もられてはじめて、非劣性検定が意味を成す。
参考書籍
丹後俊郎著 無作為化比較試験 朝倉書店 6. 非劣性の評価